映画とは別の仕方で、あるいは映画を観ることの彼方に ドゥシャン・マカヴェイエフ論2
長編全作品は、前記シネマテークで上映されている。ヴィデオ化もほとんどされている。『人間は鳥ではない』『保護なき純潔』には、マカヴェイエフ自身による自作解説インタヴューが付けられている。
長編第一作『人間は鳥ではない』はまだ行儀よく作られている。辺境の銅山町の工場に技術指導のために着任した党のエリート技術者と町の娘とのつかのまの恋。それをヌーヴェル・ヴァーグ調に描いたものと観れなくもない。ノルマ至上平義に走る工場官僚の姿が、例の紋切り型で批判的に描かれるわけでもない。
愛の不毛をテーマとする限り、過不足なく鑑賞できるだろう。冒頭に、セックス・コミッサールと呼ばれた酒場の歌手が酔いどれに殺されるエピソードが置かれている以外、それほど激しい挿話は入ってこない。技術者は工場ラインの能率化を成功させ、表賞を受けることになる。一方、ラインから外れサボタージュする労働者、銅線を身体にまきつけて盗用する者も、いくらか義務的に描かれている。
ラストに、鉱山町にサーカス芸人たちがやってくる。この部分の異化効果に、マカヴェイエフの本領が発揮されている。アクロバット師、蛇女……流浪の芸人たちも一時滞在者でしかない。人間は鳥ではないにしても、鳥のような人間たちの映像は唐突な効果をもっている。
明らかにこれは、ラインにつながれた労働者とは違った視点において描かれているのだ。生産力主義の軛に圧殺されるプロレタリートと「自由芸人」とを対比させ、体制批判を暗示したと観るのはあまりにも図式的だとしても、それほど外れてはいないだろう。
『愛の調書』は、ずっとマカヴェイエフらしい作品となっているが、暗さと閉塞状況の色濃さが気になる。ドキュメンタリー・タッチでありながら、話は煽情的な殺人事件である。井戸から引き上げられた女の死体、性科学者、犯罪学者のレクチャー、ニューズ・リールを織りまぜ、電話交換手と衛生検査官の愛の生活とその破錠を描く。力点は様々のエピソードのモンタージュにあるのだろう。
オリジナルの『保護なき純潔』は、ナチス占領下でつくられたセルビア初のトーキー映画だった。
抵抗映画であって愛のドラマだ。貧乏な青年が、継母にいじめられ金持ちの男の意のままになろうとする薄幸の美女を救い出す、という典型的なハリウッド風メロドラマだ。セルビア愛国主義の所産でもあるだろう。
製作監督主演はアクロバット師ドラゴリューブ・アレクシッチ、全くのワンマンーショー映画。鋼鉄の男として知られ、鎖を噛みきり、引きちぎり、高所の綱渡りの見世物を得意とした。占領下になって見世物を禁止され、かれは映画製作を想い立つ。撮影監督はドイツと人脈があり、フィルムを確保できた。しかし作品は公開禁止。フィルムは地中に埋められ解放後の発掘を待つことになった。
しかし、あとに製作者は対独協力者として告発されかけ、作品は映画史から消された。
マカヴェイエフ版『保護なき純潔』は、このテキスト(埋もれたフィルム)の文字通り名誉回復である。綱渡りの男アレクシッチは、少年時のマカヴェイエフのヒーローでもあった(そのことは、『A Hole in the Soul』冒頭の回想にも明らかにされていた)。そしてかれはこの埋もれた映画の再現を試みる。
この占領下につくられたメロドラマのタッチに、ゴダールらヌーヴル・ヴァーグの手法と共通のものを見い出す、とマカヴェイエフが語るとき、かれは自身の出立点をも確認していたのだろう。
再現はマカヴェイエフ一流の方法で貫かれる。「テキスト」、映画そのもの(埋もれたフィルム)の「引用」はもちろん。当時のスタッフ、出演者への四半世紀後のインタヴューが、「テキスト」の輪郭を明らかにする。これだけなら、当節の「メイキング・オブ……」の方法と同じである。
ここにプラスされ、当時のニューズ・リール、アレクシッチの現在がモンタージュされてくる。五十八歳の肉体とパワーは衰えをみせず、無邪気なばかりのマッチョ・マンの誇示が画面にあらわれる。
そればかりでなく、「テキスト」そのものも手を加えられるのだ。どんなふうにか――。
部分的に着色されるのだ。それはクライマックスになって、まるで幼児のいたずらのように画面を訪れてくる。
例えば、ヒロインの不安の表情のアップ・ショットで唇だけが鮮やかに赤く塗られているというふうに。ついに金持ち男は実力行使でヒロインを自分のものにしてしまおうとする。不安におののく女の表情、その一点だけが赤くふるえている。
ヒーローは屋上から綱を渡して、窓をうちやぶって救出にやってくる。男たちが格闘する室内、絨毯のタペストリが赤に青に輝いている。そしてやがて悪役の顔も――。傷のあざは青く、流れる血は赤く、グロテスクに輝いてくるのだった。
驚くべき異化効果だ。傍若無人のリミックスと注釈。これがマカヴェイエフの本領だ。全く手垢のついた紋切り型のラヴ・ロマンスを発掘してきて、ここで再現されているのは他ならぬマカヴェイエフのフィルムなのだ。それ以外ではなかった。
『WR オルガニズムの神秘』は、マカヴェイェフの名を世界に知らしめた。禁じられた思想家ウィルヘルム・ライヒの生涯と活動をたどるドキュメントに加えて、性と政治をめぐるおびただしいエピソードとメッセージを満載し、スキャンダラスな話題をさらった作品。
フロイトとマルクスのアンファン・テリブル、ライヒの名が六〇年代末の革命的状況に高く輝いたことは記憶に新しい。
マカヴェイエフがこの異端の思想家に接近遭遇することはいわば必然だった。〈性-政治〉の革命は、六〇年代叛乱にとっては不可欠の旗印だったろう。それを語りかけるためにマカヴェイエフの方法ほどふさわしいものはなかった、というわけだ。
ユーゴスラヴィア当局は、作品を上映禁止にするばかりか、作家を投獄しようとすらした。祖国を追われた作家マカヴェイエフの誕生である。故国がこの映画を上映するまであと十六年待たねばならなかった。
しかしそうした情勢を或る種の高みから論評する〈自由〉ほどいかがわしいものはあるまい。一つの国家では政治体制もしくは政治思想の頑迷さが『WR――OM』を拒絶したのだとすれば、他の国家では性思想の体制的頑迷さがこの作品を拒絶し続けたという動かせない事実があるのである。
幻のフィルムと呼ばれていたこの作品が日本で公開されたのは一九八九年、〈国王〉の死の直後だった。ユーゴスラヴィアより二年遅かった。
禁じられた十数年が『オルガニズムの神秘』にとって如何にとりかえしのつかない歳月だったか想像に難くないだろう。〈性‐政治〉の解放が望ましい方向には微動だはしなかったとしても、性そのもののではなく、性的刺激物の「解放」は破天荒な速度で進行したのである。伝説のヴェールを脱いだ作品は、或る種の期待に応えるほどには刺激にみちていなかったはずなのだ。
スキャンダラスな作品の主張は、しごく真面目なものだったといえるのではないか。作家の内部においては、軽業師に捧げるオマージュも異端思想家に捧げるオマージュも同列であったかもしれない。
しかし対象によって引用の質が異なるのは当然のことだ。ライヒとの共闘は不可避に、やはり、映画の中に書物の痕跡を残してしまったような気がしてならない。だから余計に、伝説をつくったほどには「あまり刺激的でないセックス・シーン」を含むこの映画が、幾分、教科書的に観られてしまったことが残念なのである。
語るに落ちることではあるけれど、マカヴェイエフの性描写はいっぱんに、それほど過激でもなんでもない。裸体にしても、いうところの行為のからみにしても、強いて好んで場面化する性癖はない。ただ、モノが少し見えようが丸見えになろうが頓着せず、おおらかにフレームを決めてしまうから結果として当該部分が映ってしまう。その回数が多いだけなのだ。
因みに、最初の三作品には、当該部分はおろか、裸体すらも出てこない。あるところにはあるのだから見えるものは見えるのだ、というのはふつうの性思想だ。それをいちいち消したりボカしたりしなければ公けにしないというわれわれの性思想が異常なのだ。とことん異常なのだ。
最近は妙な風潮で、オケケを見せる見せないもボーダーレス時代とかになっているわが国であるようだ。きわめて興行成績の良かったという「初ヘヤー解禁映画」も、見せることを許す角度、見せることを許さない角度とフレームという選別に、この体制側の性思想の現在点が透けて見えてきて、何か物哀しくなったのだ。
――閑話休題。
『スウィート・ムービー』でマカヴェイエフの越境が始まる。これが最高傑作である。
『モンテネグロ』は前作のリメイクのような作品である。タイトルは祖国の一共和国どは全く関係がない。スタイルの確率と衝撃の中和化。
前作が、フランス、カナダ、西ドイツ制作。今回は、スウェーデン、イギリス製作である。越境が映画製作を困難にすることは当然だった。
カンヌ映画祭で騒然たる話題をさらった『スウィート・ムービー』が興行的にどれほど成功したかは、ほとんど明らかにされていない。しかし次作までの七年間のブランクを考えれば、今さらそんなこと追及するまでもないだろう。
ブニュエルにおけるメキシコ時代のような環境もかれにはなかったし、ハリウッドにはかれを招くような野蛮なプロデューサーはいなかったのだ。いや、F・F・コッポラがコンラッドの『闇の奥』映画化をかれに押しつけようとした事実はあったらしいのだが。
『モンテネグロ』は「ソフィスティケイテッド・コメディ」の線の依頼だったという。むしろより悪趣味になったと想えるが、大衆受けに徹するという資本の論理は、かれを自由にしなかっただろう。
『WR――』から十年、この時期の作品の少なさが、どこまでも残念だ。
『コカコーラ・キッド』はオーストラリア映画。コカコーラ販売作戦ををめぐる一大喜劇。これがマカヴェイエフ映画の日本初公開作となった。
『マニフェスト』はユーゴスラヴィア制作のアメリカ映画。エミール・ゾラ原作を使用した片田舎の艶笑喜劇といったところ。だがこれは祖国に戻った作家のクレージーなマニフェストだ。それを読み取らずに観ることができない。『WR――』は発禁を解かれ、作家自身も帰還することができた。
しかし解体前夜の祖国にかれは何を見、何を訴えようとしたか。
『マニフェスト』のヴィデオは、ポルノそのままのパッケージだった。下品なのはいいが、節操のなさというのは許容しがたい。政治色濃厚なエロ映画だから、宣伝コピーに間違いはないが、つくづくこの作家が不幸であることにあらためて想い致った。
映画の紹介ほど言葉にとって優等的なものはない。それらは映画を観た通りに書くもの
だ。観た通りに書けるものだろうか。もしその関門を通過しても言葉は満足することができない。映画という現実の豊饒さに比べて、言葉はどれほど貧しいものなのか。言葉は少なくとも観たことに奉仕しなければならない。ところが観たものとは、観なかったものの反対証明にしかすぎない。観ることの彼方につきぬけねばならない。言葉の彼方に言葉を見つけねばならない。
だ。観た通りに書けるものだろうか。もしその関門を通過しても言葉は満足することができない。映画という現実の豊饒さに比べて、言葉はどれほど貧しいものなのか。言葉は少なくとも観たことに奉仕しなければならない。ところが観たものとは、観なかったものの反対証明にしかすぎない。観ることの彼方につきぬけねばならない。言葉の彼方に言葉を見つけねばならない。
だからここではもう、『スウィート・ムービー』についてだけ語ろう。
世界は虐殺にみちている。
愛する者を殺さねばならない。
革命の希望とはそこにしかない。
……がだ、ばれすとるあしもが望希に命革
アンナ船長とサバイバル号がどこから来てどこへ向かっていくのか、つまびらかではない。様々の革命を通過して不可視の未来にいくのか。単に、ヨーロッパの狭い運河を下っていくだけなのか。
ここに積まれているものはわずかだ。革命歌と同志殺しと砂糖菓子の誘惑と。そして、そうだ、子供たち。サバイバル号のオデッセイアは、映画の中では短く完結してしまう。最後には、この映画がつくられたテルミドールの歳月に狩られたテロリストそのまま、官憲によって壊滅させられてしまう。
じっさいに、船長アンナ・プラネッタ役の女優アンナ・プリュクナルは、このスキャンダラスな映画出演によって故国ポーランドを追われてしまう。
奴らは舳先のマルクスの眼にたまった涙を取り外した。奴らにそんなことする権利はないというのに――。
ポチョムキンの水兵がどこから来たかは明らかにされている。過去の革命からのメッセンジャーとして一九〇五年の蜂起からやってきたのだ。
そして殺される。
かれをむかえるのはアンナ船長の肉体と砂糖のベッドだ。かれは犠牲の血を供するために過去からやってくる。名前もラヴ・バクーニン。過去からやってきて、過去のための希望を語ろうとする。そのためにかれは殺されねばならないのだ。
かれは郵便配達夫、しかし水兵の恰好をしている。サバイバル号を見つけ、追いかける。かれのラヴコールは運河への放尿。当該部分は、黒くボカシてある。ボカシからほとばしる小便。
かれらは出会い、官能しあい、共にイタリアの革命歌を唱い――「アバンティ・ポポロ」、「前進せよ、人民よ」――そして愛し合った。船のブリッジの階段の上で立ったまま交わった。水夫の尻が映り、結合部分と思われるところにボカシが入る。衆人に見える場所、絞殺された過去の革命の失敗者がぶらさがるそのすぐかたわらで。
作者はこれをドイツの国立映像資料館から借りてきて、自作の中にコラージュしてみせた。
累々たる屍の群れ……五千体。
一九四〇年ソ連軍は、ポーランドに侵入、虐殺して埋めた。それらはドイツ兵によって堀り出され、戦争犯罪の記録としてフィルムに収められた。ゴルバチョフ政権のペレストロイカが正式に謝罪するまで、この事件を語ることは 一つのタブーだった。
マカヴェイエフは、それを無雑作に、引用符付きの形であるが、そのまま記録として投げ出してみせたのである。ドイツ兵は死体をまるでガラクタのように扱っている。フィルムに取って残すことだけが肝腎だったのである。
……かれは風呂の中で語り終わる。それとも、虐殺がかれの悪夢の中に記憶となって蘇り、かれはその映像を幻のように再現してみせたのだろうか。身体を洗った水兵は、再びアンナ船長との愛の営みに……。
今度は砂糖をしきつめたベッドがかれを待っている。ベッドに、ダイヴィングする水兵。うしろから局部がまる見えのショットなのでボカシ。
しかし船長はかれにこたえる前に、子供たちを誘惑し始めた。船内に招待された四人の子供たち。アンナはお菓子を与え、薄物を脱ぎながらストリップ・ティーズの誘惑。身悶えし、子供たちの性器に手を伸ばし……一人一人、殺していく。
窓にはられたトロツキイの肖像は何を見ているのか。
そしてようやくアンナ船長は砂糖のベッドに……砂糖の中でセックス。快楽の余韻の中で彼女は水兵の腹をナイフでえぐる。砂糖の中からふきだしてくる血のねばりが妙に毒々しい。船の舳先のマルクスの眼には大粒の涙が一つ。同志討ちの激しさ徹底性こそが、革命にとってのカであり希望である――。
これはむしろ背理としてのみ理解されてきた事柄であった。
しかしすべてはスターリニストによって「裏切られた革命」の権力意志によって、あたかも教義のように正当化きれてきた。しかし権力意志をもたない粛清がもしあるとすれば、それはどういうものなのか。自らを頽廃させることのない同志殺しがあるとすれば、それはどういうものなのか。
ささやかなものであっても記憶にやきついた連合赤軍の十六名の死者たちは、こうした映像の彼方に確かに立ち続けている。
砂糖にまみれた『スウィート・ムービー』の死の甘さは、同志の血の苦さの仮象だった。
愛した人はみな死んだ。甘く、甘く、甘く……マルクスの涙。
『スウィート・ムービー』にはもう一つのオデッセイアがあった。
ミスワールド84の受難……黄金のちんぽこから始まって、全身チョコレートにまみれるスウィート・クライマックスヘと至る。もちろん金粉塗りの当該部分は画面にボカシをまとってしか現れず、字幕の説明によって観客は映像を理解する他ないのであるが。
早速、ミスター・ドルから花嫁解雇をいいわたされたミスワールド84は、身一つで放り出され、用心棒の黒人マッチョマンにもらい下げられてしまう。マッチョマンは逸物を誇示し、フリチン縄飛びをやってみせる――この面白い場面も、当該部分を切って拡大修正をほどこされているので、上半身が見えるだけ、大して面白くない。
自分の肉体を誇示するしか興味のないこの男によって、彼女はトランク詰めにされてパリまで空輸されてしまう。トランクから脱出したミスワールド84、真ッ裸の上に毛布をかぶった姿でエッフェル塔にやってくる。
そこではスペインの人気俳優が撮影しているのだった。撮影のあと、塔の物影で、彼女は俳優と立ったままの体位でセックスを始める。
毛布だけの恰好が幸いしたのだが、際中に、修道尼のグループに声をかけられ、膣痙攣を起こしてしまうのだ。二人一緒にかつぎこまれるのは病院ではなくて、ホテルの調理場だ。合体が解かれたあとミスワールド84は哀しくて、卵をいくつもいくつも自分の顔に叩きつけて割るのだった。
傷心の彼女はウィーンのセラピー・コミューンに運びこまれる。ここでミスワールド84の受難は頂点に連する。
ここまで二つのオデッセイアは関連するごとなく並行して進んできた。サバイバル号の航海に比べて、ミスワールド84のそれは、どちらかといえば軽やかなトラジ・コメディに一貫していた。ところがコミューンの挿話が現れると、画面はがぜん重みを加えるのだ。
オットー・ミュールと銀河コミューンが登場してくるからである。或る意味では、作品の最大の焦点こそこのコミューンのエピソードだといえるのだ。
かれらは完全に私有制と私有家族制を否定した共同体で生活している。そしてオットー・ミュールとかれのマテリアル・ハプニングは六〇年代末のアンダーグラウンド映画の神話を形作った。
作品は短く、コミューンの実験セラピーの記録でもあったのかもしれない。裸の男女に同じく裸の男女が小便をかけまくったり、ペンキをぶちまけたりするフィルムの異様な衝撃は、しばらく忘れられないものだった。
七週間かかった『スウィート・ムービー』の撮影のうち、七日間はこのコミューンのシーンにあてられ、共同制作としてつくられたとマカヴェイエフは明らかにしている。一日一日は、ミルクの日とか、食べ物の日とか、舌を切る日とか、クソの日とか、ゲロの日とか、幼児に還る日とか、名付けられたのだろう。
この騒乱と狂騒にはつりあう言葉がない。「酒池肉林」といえばいえなくもないが、そんな生やさしいものではない。
一人がズボンの中からどすぐろい一物を取り出してナイフで切り刻んだ――じつは牛の舌をペニスに見立てたのだ――かと思うと一人はテーブルに向って長々と放尿しながら口からゲロゲロと反吐をはく……。二人の男が二枚の皿をもって対峙し、クソの太さを競争し合う……。
ここには別様に撮られ、そしておそろしい凝縮と混乱のうちに編集され直し、異様な衝撃を増幅されたマテリアル・ハプニングがある。マカヴェイエフによってつくられたオットー・ミュール映画――という怪物的な断片であるのだ。これは。
理念的にはともかく、これは作品全体でいって、現実的にはもっともきつい地獄めぐりだったのだろう。七日間の最後の一日は、死の日、血の日になるはずだったと監督は語っている。こういうシーンが構想された。
《大きなベッドにまっ白なきれいなシーツをかける、そこに主演女優のキャロルが裸でベッドに横たわって羊を抱きかかえてるんだ。それからカメラが近付いていく。ベッドのまわりには他の女たち全員が裸で円になって見守っている。それからキャロルはナイフを手にとって羊を刺し始める、そして叫ぶ。「母親を殺してるんだ、母親を殺してるんだ」って。羊は彼女の腕に抱かれたまま死んで、彼女は全身血まみれになる。血は他の女たちにも飛び散って、彼女らもこの羊の血をうけとめる。彼女たちの母親との関係を処する儀式を執り行なうというのが彼女たちの提案だったんだ。ぼくは、結構きつい感じがするけど、撮るとしたら君達との最後の日にしようといった。ちょっと怖かったからね》
アンナ船長の殺人はドラマの中だった。しかしこの羊殺しは現実の流血だ。そしてその血を体中に浴びねばならないのだ。
《全体のコンセプトは、キャロルがこの革命の船、変身の船、新しい生命の船に来て、幼児期や悪夢をくぐって、狂気をくぐりぬける、そういう旅路で、きれいになって出てくるってことだったんだ。でも、それは女優のキャロルにはきつすぎた。彼女は六日目の撮影を終えると、もうそれ以上できなくなってしまった。だから最後の「血の日・死の日」はやらなかった》
七日間のエンディングのシーンは、全員が裸になってインタナショナルをバックに踊る場面だ。
ミスワールド84――キャロル・ロールは片隅ですすり泣いている。
こうした試行の数々は、コミーンの治療思想の質をよく語っている。肉体はマテリアルであり、それが突発的に異物に汚されることを通して、逆に、精神の抑圧が解かれ浄化されていく。そういう儀式を共同体化すること。映画スタッフの少なからぬ部分がこうした実験に耐えうるガッツをもたなかったことは無理もない。こうした実験は自らの内奥から呼ぴおこされないかぎり、脅威と感じられる他ないのである。
主演女優の一人は国を追われ、一人は途中で音をあげてしまった。それがこの映画だ。
羊の血のかわりに用意されたのはチョコレートだ。ミスワールド84はチョコレートを浴び、映画は文字通りの『スウィート・ムービー』になった。砂糖のベッドの上の同志殺しとも話が通底することになった。
チョコレートいがい何も身につけていないミスワールド84。カラスのように真っ黒だ。驚くべきことは、驚いてはいけないのかもしれないが、このカラスのような裸体の映像すら〈修正〉されているという事実だ。まっくろの身体の当該部分が黒くボカシてある。その上、全体を色濃く修正してあるというので、ほとんどぼんやりとしか見えないのだが。ここでボカシは健在である。
これは『スウィート・ムービー』の十数ケ所の〈修正〉の中でも、もっとも馬鹿気だ成果なのだ。このような日本版ができるために、二百万円の経費が別にかかったという。
控え目に数えても、この作品でボカシになった当該部分では男性器のほうが回数が多いのである。このことが告げているのは、性思想の、というより性の検閲思想の不定見さである。要するに当該部分を見せないで済ますという形式主義があるばかりなのである。
マカヴェイェフ映画の衝撃は検閲によって弱められる質のものではない。ただボカシの存在によって観る側の卑少さを余分に感じ取てしまうというマイナスがあるのみだ。検閲が有効なのは、当該部分を見せるためだけにつくられた物件に対してである。そうでない場合は、隠されることによって逆に、われわれの〈性‐政治〉の貧しさが暴き出さねてくるのみなのである。
映画のラストシーンは意義深いものだ。すでにアンナ船長は捕えられ連行された。サバイバル号から子供たちの死体も運び出された。それらはビニール袋に包まれ、河岸に並べられた。
ギリシャ語のテーマ曲「野原の子供たち」がバックに流れてくる。――そして子供たちが袋を破って、起き上がってくるのだ。
生き返って。
およそ信じがたい話の展開だが、ここにだけ単純に光明が見い出せたのである。やっと救われたと思えたのだ。それで全体の衝撃がやわらいだわけではないのだけれど。せめてこのような救いは必要だと思えたのだ。
最後に付け加えることはあるだろうか。
例えば『マニフェスト』について。一つの政治的寓話を解釈してみること。テロリズムとエロチシズムの哄笑にみちた寓話を。
それは必要であるだろうか。
一九二〇年、中欧。新しい権力が打ち樹てられ、新しい政府が機能し始める。それでもアイスクリームは売れていた、と。映画はそうして始まる。 これがバルカンの一王国の話でないと考えるほうがむずかしい。片田舎を走る列車は橋にさしかかる。名家の令嬢スヴェトラーナは故郷に戻ってくる。王を暗殺するテロリストの任務をもって。彼女は実行者である教師に銃を渡す役目である。同じ列車に乗って保安警察長アヴアンティもやってくる。 警察署長は教師を逮捕し、馬に乗った旧権力者の銅像を破壊する。ところが上半身だけ壊されたその像にモデルをまたがらせて、いかがわしい写真を撮っている写真屋がいる。教師はサナトリウムに送られ、永久運動の牢獄にぶちこまれる。ローターの内部を走り続けていれば、その装置も永久に回り続けているのだ。 令嬢が家に戻った夜中、執事がかつての体の関係の修復を迫って忍び込んでくる。言葉では拒否しても体は拒めない女だった。その窓辺を、令嬢に恋慕する郵便局員が、熱いまなざしを送るのだった。令嬢はパンに隠して銃を教師に渡すのだが。 教師リリーは子供たちを俗悪なものから遠去けようとする堅物。ところが遠足に出かけた森では写真屋がモデルと熱くなっているし。王の警護任務も忘れた保安警察長がアイスクリーム売りの少女を金でものにしたところ。子供たちは覗き見に大喜びだが、リリーは激怒してアヴァンティを縛り上げてしまう。そこに王の一行が来合わすのだった。 逆に捕ったのはリリーで、これもサナトリウムに送られる。続いて、テロリストの洗脳装置にいたく興味を示す王がここを訪れる。どの説明を受けても痴呆のように笑っている王。ここが暗殺の決行場所になるはずだった。だが銃を渡されていた教師はすでに転向していて、永久運動装置の中を「前進!前進!アバンティ・アバンティ」と叫んで走りつづけるのみだ。それを見て更に笑いころげる王である。
夜は令嬢邸での歓迎パーティ。スヴェトラーナは決行が不発に終わったことを知り、代わりの方法をとろうとするが。執事また現れて色を迫る。 危急存亡、しかしかれは転んで頭を打ってあえない最期を遂げる。繊鍛にくるんで死体を隠したのと王の一行が部屋に入ってくるのと同時だった。決行の機会は去り、途方に暮れる令嬢。窓辺に現れたのは郵便局長、長年の想いのたけを打ち明けるときだった。 二人は激しく燃え……庭でもいたるところで性の饗宴が。もちろんアヴァンティも令嬢の母とねんごろにやっていた。それを映している写真屋。 そのショットを横切って郵便局長が執事の死体をかついでいく。情事のあとに処理を押しつけられたのだ。しかし橋まで運んで死体を落すときに、自分も一緒に落下、純情男はあえなく絶命してしまう。
リリーはサナトリウムを脱出。教師も救おうとするが、かれは永遠の牢獄から出ることを拒否する。
一夜明けて、何事もなかったように列車は町を離れ。その客室には再び令嬢と保安警察長の姿が。そして銃を手にし、今やテロリストの意志を体現したリリーが列車の屋根を走り、二人に迫る。
窓から逆さ向けに顔を出し、銃声一発。暗転して映画は終わる。
片想いの純情男は令嬢に二十七通の手紙を書いたと告白するのだが、この数字は、マカヴェイエフが自分の長編第一作を語ったときそこには二十七種の灰色が描かれていると誇った数と一致するし、果してしからば、かれは祖国への渇望の想いを二十七回訴えたのかもしれず、あるいは単純にかれが企画をあたためて実現しなかった無念のフィルムがその数だけ、かれの胸に墓碑銘のように刻まれてあったのか。
この寓話において、猥雑に暴れまわるすべての人物が、自分の意図については挫折しているのである。ことごとくすべて、一人の例外もなく。
王は暗殺されず――じっさいの事件は一九三四年のことだ――河も橋も列車も、永遠の待機主義を映すようにも、悠々と画面を横切っている。
解体前夜の祖国に、作家はどんなマニフェストをおくったのか?
いや、もはやそうした裏目読みはすまい。
性も政治も、自在に読み解くためには、われわれはあまりに弱い民族だ。性においても政治においてもあまりに弱い。性も政治もこの国にあっては不徹底なボカシの彼方にあるのではないか。
**これを書くにあたり『イメージ・フォーラム』1989年4月号「マカヴィエフあるいはヘンタイ映画の起源」――ダゲレオ出版、および『マカヴィエフ・フィルム・コレクション』リーフレット――コムストック、を参考にした。
同時代批評16号 1994.1
2015-02-05 09:42 2015-02-06 12:42 2015-02-06 20:13
参考
















%20-%20Filme%20Completo%20Legendado.avi_000053869.jpg)















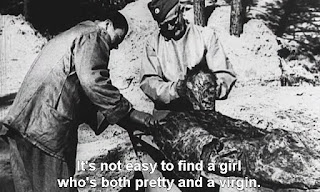































コメント
コメントを投稿